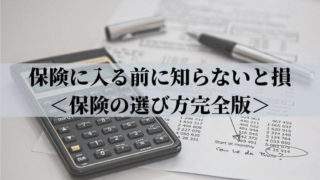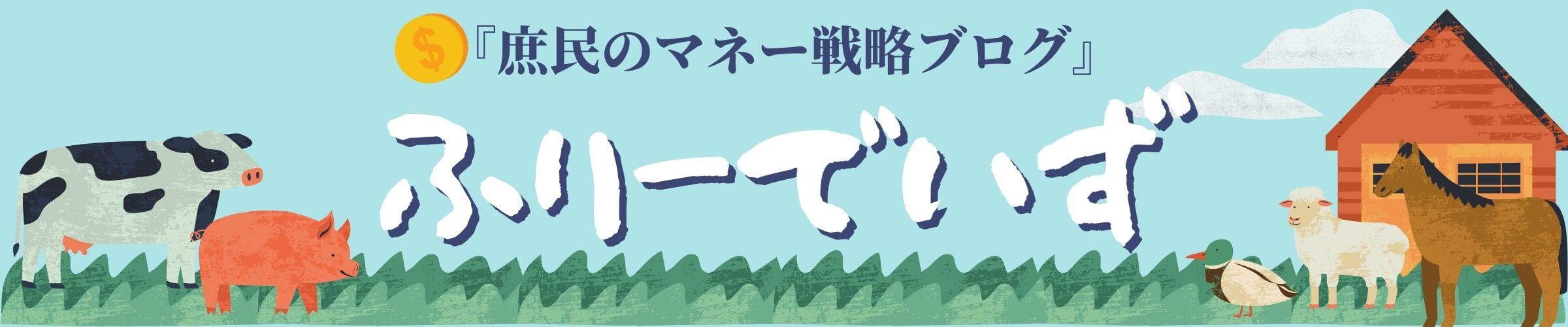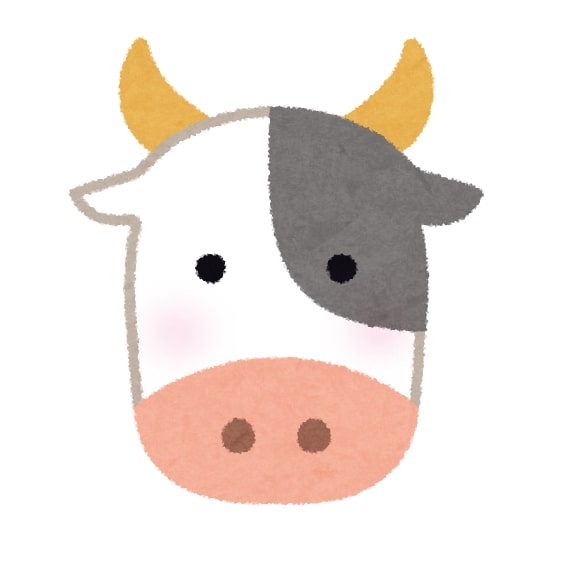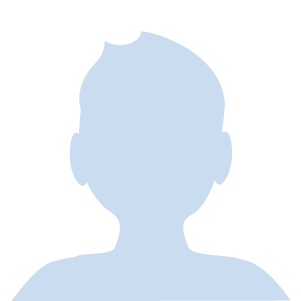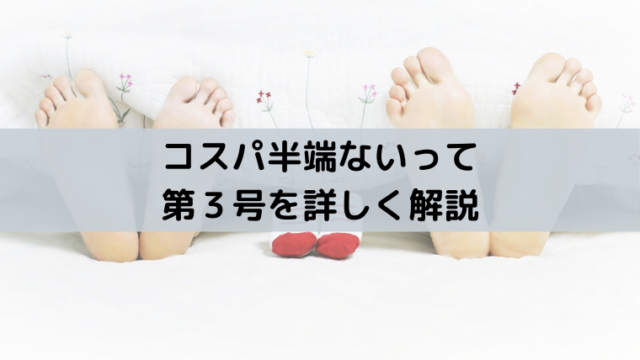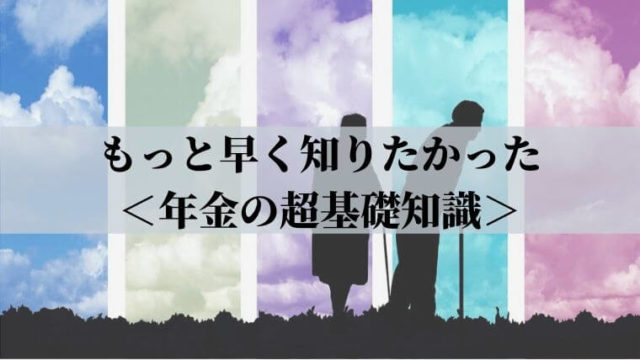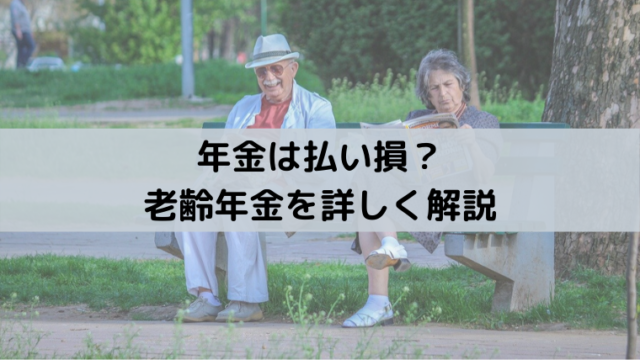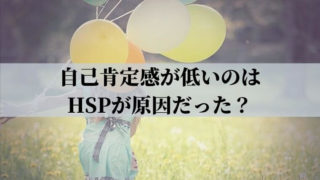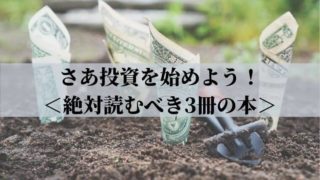この記事を読むとわかること
- そもそも年金とは何か
- どういうときに障害年金をうけとれるのか
- 障害基礎年金と障害厚生年金
- 障害年金の受け取り4パターン
- 受け取れる年金額の計算
そもそも年金とは?
日本国内に住む20歳から60歳までの人は国民年金への加入が義務となっています。
加入するかしないか選べるものではありません。
また、社会保険に加入している会社で働く人は20歳未満から70歳までは厚生年金の加入が義務となっています。
厚生年金に加入し保険料を支払っている人は、国民年金の保険料も支払っている扱いとなります。

障害年金とは?
年金は「もしもの時に収入がなくなってしまうのを防ぐこと」を目的とした保険であり、
(1)年を取って働けなくなった時
(2)障害を負って働けなくなった時
(3)一家の大黒柱が亡くなった時
に年金を受け取ることができる仕組みとなっています。
もちろん保険なのでちゃんと保険料を支払っていないと受け取ることができません。


この記事で取り上げるのは
(2)障害を負って働けなくなった時に受け取れる年金。その名も障害年金です。
一般的には
国民年金に加入していた人が受け取れる年金は障害基礎年金と呼び
厚生年金に加入していた人が受け取れる年金は障害厚生年金と呼びます。
障害年金をもらえるのはどういうとき?
障害を負ってしまい働けなくなった時に障害年金がもらえることはここまでの説明で理解していただけたと思います。
では「いつもらえるのか」を考えるときには初診日が重要になってきます。
初診日とは「障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日」のことを指します。
そして初診日から1年6か月を経過した日(もしくは症状が固定した日)に障害の状態にある場合、その日を「障害認定日」とし年金を請求することができます。
あくまで初診日が基準となるので思っていたよりも過去にさかのぼって考えないといけない場合もあります。
ただし年金を受け取るにはきちんと保険料を納めている必要があります。

注意していただきたいのは初診日の前日時点での保険料の納付状況で権利が決まるということです。
これは当たり前ですが、初診日以降の納付状況となると事故にあってからまとめて保険料を支払うこともできてしまうからですね。
ちゃんと払っていれば問題ありません。
そして受け取れる年金の種類と金額は
- 初診日時点でどの年金制度に加入していたか。
- 障害の程度はどのくらいか
によって決まってきます。

国民年金の保険料と障害基礎年金の関係
ではいくらくらいもらえるのでしょうか。保険料との関係を見ていきましょう。
国民年金の保険料は月額16,410円です。(令和元年度)
国民年金加入中に初診日がある場合は障害基礎年金が受け取れます。
ただし障害の程度によって受け取れる金額は異なり、程度の重い方から障害1級と障害2級に分けられます。
(令和元年度)
障害1級:年額975,125円(780,100円×1.25)+子の加算
障害2級:年額780,100円+子の加算
※子の加算は第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円。
ちなみに年金制度での子とは以下の者を表します。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障がい者
20歳で障害を負っても40歳で障害を負っても金額は一律です。
例として、障害2級で子が1人いる場合は
780,100円+224,500円=1,004,600円(年額)
となります。
ちなみに保険料を払い始める20歳前の障害であっても20歳から障害基礎年金を受け取ることができます。(1円も払わずに障害年金を受け取ることになるため所得によって制限などあり。)
厚生年金の保険料と障害厚生年金の関係
では続いては厚生年金の保険料と障害厚生年金の関係を見ていきましょう。
厚生年金の保険料は月給によって決まるため、平均月給30万円で働いており、30歳で2級障害を負ってしまった人をモデルとします。
・30歳で2級障害を負った。
この場合厚生年金の保険料は30万円×18.3%=月額54,900円となります。ただし、厚生年金加入者はこの半額を会社側が負担してくれるため実際にモデルAが支払う保険料は月額27,450円となります。
厚生年金加入中に初診日がある場合は障害厚生年金を受け取ることができます。さらに、障害等級が1級、2級の場合には障害基礎年金分も受け取ることができます。

障害の程度によって受け取れる金額は異なり、障害の程度が重い方から障害1級、障害2級、障害3級、軽度の障害の4つに分けられます。
障害厚生年金の金額はざっくり以下の式で計算できます。
Ⓐ:平均月給×(5.481/1000)×加入月数
(ただし加入月数が300月に満たない場合は300月で計算します。)
加入後間もない方でも300月分は最低限確保しますよという仕組みになっているわけです。
(令和元年度)
障害1級:(Ⓐ×1.25)+配偶者の加給年金額+障害基礎年金の1級分
障害2級:Ⓐ+配偶者の加給年金額+障害基礎年金の2級分
障害3級:Ⓐ+配偶者の加給年金額(最低保証額585,100円)
軽度の障害:一時金としてⒶ×2(最低保証額1,170,200円)
※配偶者の加給年金額とはその方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に224,500円が加算されます。
・30歳で2級障害を負った。
今回の例で受け取れる金額は
30万円×(5.481/1000)×300月+ 780,100円=1,273,390円(年額)
となります。
ちなみに生計維持している配偶者と子が1人いる場合は
1,273,390円+224,500円+224,500円=1,722,390円(年額)
となります。
まとめ
年金は高齢者がもらうものであり、若いうちは関係ないと思っていた方がほとんどではないでしょうか。私も大学卒業まで知りませんでした。
しかし実際年金は保険の役割を担っており、今回の記事の通り障害年金という制度もあります。これは若い世代も無関係ではありません。
むしろ障害年金の存在を知らなかったために、民間の保険会社に搾取されている可能性すらあります。(私がそうでした。)
たしかにもしもの時に障害年金だけでは十分な金額とは言えないでしょう。
しかしこれを知っているか知らないかでは民間の保険に対する考え方や安心感は大きく異なってきます。
知らなかった方は今一度保険を見直してみてはいかがでしょうか。