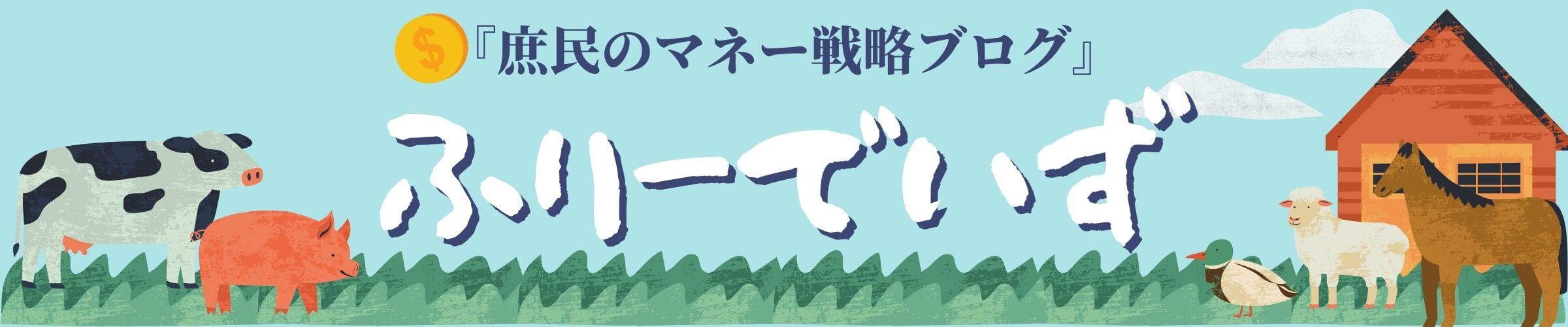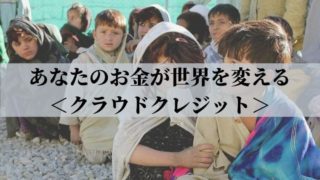株を購入すると配当金がもらえることはなんとなく理解している方も多いはず。
でも「配当控除」って聞いたことありますか?
配当控除は税額控除の1つであり、税金を安く抑える効果があります。
そして実は低収入・低所得の人ほど配当控除を活用すべきなんです!
今回はその理由と実際にどれくらいお得になるかの計算方法をご紹介!
低所得の方向けにこの記事を書きましたが、課税所得900万円以下の方であれば基本的には配当控除を利用した方が税金は安くなります。
配当とは?
会社が年間で出した利益の一部を、株主に還元する仕組みが「配当金」です。会社は株式を発行することで投資家から資金を集め、その資金を元手に事業を行って儲けを狙います。配当金は会社が儲かったら、その一部をお金を出してくれた株主に渡すという意味で支払われる株主の利益です。
(引用元:LINE証券)
会社というのは株を発行し、その株の購入資金を資本として経営が行われます。
つまり、株主のおかげで会社が成り立っているわけですね。
ただしボランティアではないので、株主も何の見返りも求めず資金を提供しているわけではありません。
そこで登場するのが「配当金」!
会社は利益が出たらその一部を配当金として株主に還元するのが一般的です。
「会社を応援してくれてありがとう。はい。そのお礼です。」といった感じでしょうか。
安定して配当金を出している企業は投資家からもやはり人気があるため配当金に力を入れている企業も少なくありません。
配当金にかかる税金は?
配当金は特定口座であれば基本的に源泉徴収され、税率は20.315%となっています。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
つまり基本的には約20%の税金が勝手に引かれるんだと理解してもらえれば十分です!
配当控除とは?
基本的には約20%の税金が引かれるわけですが、20%って税金高すぎませんか?
そんな方に知っておいて欲しいのが「配当控除」!
- 国内株式の配当金について総合課税を選択して確定申告をした時に、適用されるもの。
- 配当金に一定の割合をかけた金額が所得税・住民税から控除。
確定申告と聞くだけでめんどくさそうと感じるかもしれませんが、やる価値あり!
配当控除はなぜあるのか
国内株式の配当金は法人の所得に法人税が課税された後に株主に分配されるものであり、配当金を受け取った個人にも所得税や住民税を課税すると二重の課税となってしまいます。
配当控除はこの二重課税を調整する意味で用意されている税額控除です。
配当控除の割合は?
(課税総所得金額が1,000万円以下の場合)
配当所得の金額×10%
配当所得の金額×2.8%
配当控除は税額控除だから税金の額を大きく減らすことができる!
税額控除とは?
では税額控除とは何なのでしょうか。

税金の計算は上の図のような流れとなっています。
収入から所得控除分を引いて残った課税所得に税率をかけて税金の額が決まるわけですね。
詳しく知りたい方はこちらの記事で確認しておきましょう。
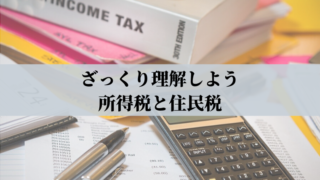
ここで税額控除とはどの部分にあたるのかというと、最後の税金の額が決まった後に力を発揮します。

税額控除は計算された税金額から控除することができます。
例えば計算された税金額が10,000円で、税額控除が3,000円だとすると
10,000円ー3,000円=7,000円
つまり7,000円が支払う税金額となります。

全体の流れとしては上記の図のようになるわけですね!
金持ちが株を買う理由
低収入こそ配当控除を使うべき理由を紹介する前にここで金持ちが株を買う理由を紹介します。
ぜひあなたがお金持ちになった際の参考にしてください!
高収入の人ほど税金が高い
日本の所得税は累進課税制度となっており、稼ぎが多い人ほど税金が高くなるように設定されています。
例えば所得金額が40,000,000円を超えた分については45%の税率が課せられます。
住民税の10%を合わせると55%程度の税金を支払う必要があるわけですね。
せっかく稼いでも半分以上税金でもっていかれてしまいます。
そこで株を買い、配当金を上手く利用するわけです。
配当金は税金からの逃げ道
なぜ配当金を利用するといいのでしょうか。
繰り返しになりますが、配当金は特定口座であれば基本的に源泉徴収され、税率は20.315%となっています。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
つまりどんなに稼いでいても約20%の税金を支払うだけで済むわけです。
詳細は省きますが課税所得が900万円を超える方はこの源泉徴収を利用することで税金が安く抑えられます。
これは申告不要制度と呼ばれ、確定申告をする必要もありません。
低収入こそ配当控除の理由
課税所得が195万円以下の人の場合、税率は約15%(所得税5%、住民税10%)です。
つまり20%の税金が源泉徴収されてしまうのは損なわけです。
では低収入の人はどうすればよいのでしょうか。
ここで重要なのが「配当控除」です。
まず配当控除を利用するためには総合課税を利用する必要があります。
総合課税というのは会社の給料などに配当金の収入も含めて税金を計算します。
ただし配当控除(所得税:10%、住民税:2.8%の税額控除)があるため税金はかなり安く抑えられるわけですね。
会社員としての給料が増えても約15%(社会保険料等を含めればもっと)が税金でもっていかれますが、配当金で受け取れば低所得の方ほど税金がかからない計算となります!
配当控除の計算方法
例えば給料の課税所得が100万円の人が10万円の配当金を受け取った場合を考えてみましょう。
所得税編
まず課税所得が100万円の場合、税率は5%なので5万円の所得税を納める必要があります。
総合課税で配当金も含める場合には課税所得が110万円となるのでその5%は5.5万円となります。
配当金所得が10万円増えたことで5,000円所得税が増えました。
ここで配当控除を適用します。
配当控除の金額は10万円の10%なので1万円です。
これが税額控除となるので
5.5万円ー1万円=4.5万円
が支払う所得税額となります。
あれ?配当所得が増えたはずなのに増える前より所得税が安くなってる!
住民税編
まず課税所得が100万円の場合、税率は10%なので10万円の所得税を納める必要があります。(※本来所得税と住民税では課税所得の計算は少し異なります。)
総合課税で配当金も含める場合には課税所得が110万円となるのでその10%は11万円となります。
配当金所得が10万円増えたことで1万円住民税が増えました。
ここで配当控除を適用します。
配当控除の金額は10万円の2.8%なので2,800円です。
これが税額控除となるので
11万円ー2,800円=107,200円
が支払う住民税額となります。
所得税ほどの控除はありませんが税金が安くなってますね!
所得税と住民税を合わせると
上記の計算を合算して考えると本来は
所得税を5.5万円
住民税を11万円
合計16.5万円支払うはずでしたが
税額控除後は
所得税が4.5万円
住民税が107,200円
合計152,200円。税額控除により12,800円税金が安くなりました。

配当金がなく課税所得100万円だけの時、税金の額は15万円(所得税5万円、住民税10万円)であることを考慮すると
配当金10万円の収入が増えたにもかかわらず税金の額は
152,200円ー150,000円=2,200円しか増えていないわけです。
これは税率2.2%ということであり、本来約20%の税率であることを考えればかなりの節税になることがお分かりいただけるでしょう。
低所得者こそ確定申告をして配当控除を利用しましょう!
さらに節税したい人は
実はこれよりもさらに節税になる方法があります。(少し上級者向け)
それがずばり所得税と住民税で課税方式を分ける方法です!
繰り返しになりますが、配当金は特定口座であれば基本的に源泉徴収され、税率は20.315%となっています。(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
所得税に関しては確定申告をし、総合課税で配当控除を利用した方が税金がぐっと安くなるのは先ほど紹介した例の通りです。
- 源泉徴収時15%➡確定申告時5%
- さらに配当控除10%が適用
確定申告時の税率は実質-5%。
しかし住民税に関しては確定申告をするとむしろ税金が高くなってしまいます。
- 源泉徴収時5%➡確定申告時10%
- 配当控除2.8%が適用
確定申告時の税率は実質7.2%。
これなら住民税だけ申告をしないで5%の源泉徴収の方がいいのになって思いませんか?
でもそんなうまい話あるわけが。。あるんです!
お住まいの市区町村の窓口に申告することで所得税と住民税の課税方式を分けることができます。
詳しくは各市区町村の窓口でご確認ください。
ちなみにこのように所得税は確定申告をして、住民税は申告をしない方式にした場合。
所得税が-5%・住民税が5%なので、配当金にかかる税金を実質0にすることができます。(課税所得が330万円以下の場合)
配当控除を利用するデメリット
このように配当控除を利用することで税金を安く抑えることができるのは大きなメリットです。
ただしデメリットになる場合もありますので以下の点はご注意ください。
- 確定申告で総合課税となると所得が増えることになるため配偶者控除や扶養控除の要件から外れないか注意が必要。
- 所得が増えることにより国民健康保険や後期高齢者医療の保険料が高くなる可能性あり。
まとめ
- 配当金には約20%の税金がかかる
- 確定申告をすれば配当控除が使える
- 配当控除は税額控除の一種
- 所得税:配当の10% 住民税:配当の2.8%が控除できる
- 所得が増えることでデメリットになる場合もある
いかがでしたでしょうか。
配当控除なんて全く聞いたことがない方がほとんどだと思います。
私自身この事実を知った時には目から鱗でしたし、もっと早く知りたかったと感じました。
まずは多くの方に配当控除について知ってほしい。
そして低所得の方ほど配当控除を上手く活用して手元に残るお金を少しでも増やしてほしいと思いこの記事を書きました。
知らずに損する人が1人でも減りますように。