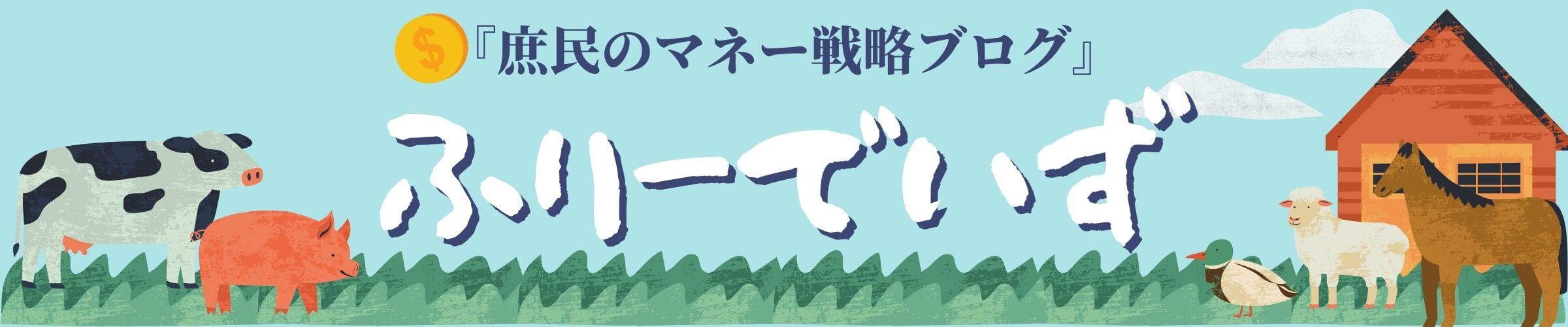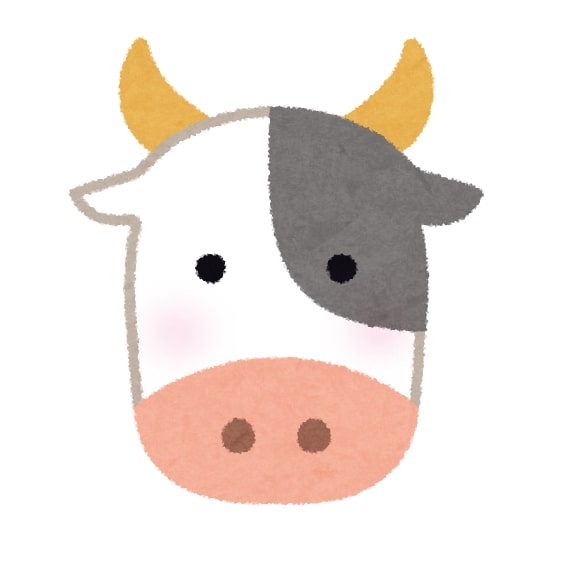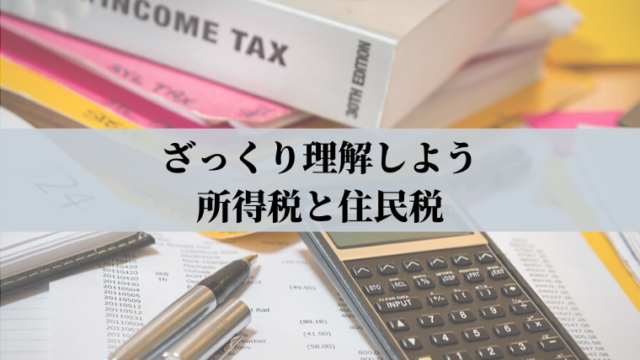Step1でお金の考え方がわかったところで
続いては「お金の守り方」について学んでいきましょう!
Step1がまだの方はこちらからどうぞ


Step2は制度を利用した手元に残るお金を増やす方法についても紹介していきます。
Step1より少し深い内容になりますが、できるだけわかりやすく紹介していきますので頑張って勉強していきましょう。
Step2.お金の守り方
~戦略6~ ATM・振込手数料を無料に

銀行にお金を預けていればお金が減ることはない。
それは本当でしょうか?
令和3年現在、銀行の預金金利は0.001%。
100万円を1年間預けていても受け取れる利息は10円にしかなりません。
(正確には税金が引かれるため8円程度)
その一方で振り込みやATMで仕方なく手数料を払っていませんか?
これでは銀行にお金を預けているだけでお金が減っていきます。
例えばある銀行ではATM利用手数料で220円かかります。
利息で元を取ろうと思ったら2200万円ほどを1年間預けていなければなりません。
ではどうすればよいのか。
ATM利用や振込手数料が無料の銀行を選べばいいわけです。
どこがいいのかよくわからない方は今のところ「住信SBIネット銀行」がおすすめです。
ATM利用手数料・他行宛て振り込み手数料がそれぞれ月5回無料!
しかも定額自動入金・定額自動振込サービスもあります。
騙されたと思って口座開設しておいて損は無いネットバンクです。
詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ
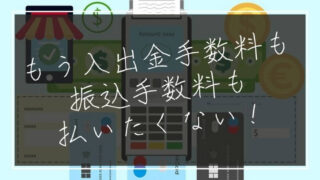
~戦略7~ ポイントをフル活用

あなたはポイントを活用してますか?
今で言えば、楽天ポイントやPayPayボーナスを使っていないともったいない!
もし使っていない方は普段のお買い物を楽天市場やYahoo!ショッピングでするだけでポイントが貯まります。
実際にどれくらい貯まるのか、例として私の累計楽天ポイントを見てみましょう。

累計約36万ポイントも貯まっていることがわかりました。
通常クレジットカードを利用していると100円の利用につき1ポイントがもらえます。
そんなわけありませんよね笑
楽天市場もYahoo!ショッピングも使い方次第でポイント還元率が大きく変わってきます。

私の場合はキャンペーンなどを上手く活用することで平均約10%程度のポイント還元があります。
10%ですよ!
使い方次第ではもっと還元を受けることも可能です。
よくわからないからといって使わないでいるだけで損しているかもしれません。
ただし、ポイントのために買い物をしてしまっては本末転倒です。
あくまでポイントは必要なものを買うときについてくるおまけだと認識しておきましょう。
ポイントを投資に活用する方法などもおすすめですが、
私のおすすめポイント活用方法としては「コンビニの支払いに利用する」です!
とても分かりやすく、簡単な方法ですが節約の効果もとても大きいのです。
コンビニを利用しすぎると出費が嵩む。
でもわかっていてもついつい買っちゃう。
そんな経験はありませんか?
とても気持ちはわかります。
そこでコンビニではポイントしか使わないというルールにしてしまいましょう!
逆に言えばポイントならいくら使ってもいいということです。
節約ばかりで浪費が少なくなっても面白みがありません。
無駄な出費は抑える。でも時には浪費も必要。
その両方を満たすのが、「コンビニでのポイント活用」です!
是非お試しください。
~戦略8~ 必要な保険診断

保険になんとなく入っていませんか?
保険は自分や身内に不幸が起こった時に保険金が受け取れるため負のギャンブルとも言われています。
保険は上手く使えばこれ以上ないありがたい制度なのですが、使い方を間違えると固定費が膨らむ大きな要因となってしまいます。
Step1で社会保険制度のことが少しわかっていれば、もしもの時の保障が手厚いことはご理解いただけているはず。
つまり、原則としては万が一の際に社会保険と貯金では足りない事柄には保険をかければいいわけです。
例えば
- 小さな子どもがいて、自分が死んだら家族が生きていけない場合の生命保険
- 自動車でコンビニに突っ込んでしまった場合の損害賠償に備えた自動車保険
など。
死んで大金を残すより、生きている今豊かにお金を使う方法を考えませんか?
って思うかもしれません。
そんな時はマネーフォワードの保険診断をやってみてください。
簡単な情報を入力するだけで万が一の際にはどれくらいのお金が不足する可能性があるのか、またあなたに必要な保険がすぐに分かるようになっています。
もちろん無料です。
社会保険についてもきちんと考慮されているため信用できますね。
詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ

~戦略9~ 生命保険料控除

~戦略8~で保険が必要だと診断された場合には保険に入った方が良いです。
保険料としての固定費が増えますが、支払った保険料の一部は所得控除になります。
Step1で税金の計算方法について理解できていますでしょうか?
おさらいしておきますと、税金は収入の全ての金額で計算されるわけではなく、収入から様々な所得控除分を差し引いて残った金額から計算されます。
つまり所得控除が多いほど税金は安く済むことになります。
生命保険料控除も所得控除の一種なので税金を抑えることができるというわけですね。
ただし「節税金額<<<毎月の保険料の支払い」なので生命保険料控除のために保険に入るのはおすすめしません。
ちなみに生命保険料控除という名前ではありますが、生命保険だけでなく介護医療保険や個人年金保険も控除の対象となります。
節税となる金額はあなたの収入金額等によっても変わるため詳しくはこちらの記事をご覧ください。

~戦略10~ ふるさと納税

ふるさと納税って聞いたことはあると思いますが、どういう制度かわかっていますか?
ざっくり説明すると、「自分で選んだ市町村に寄付をすることで返礼品がもらえる」という制度です。
ふるさと納税すると節税できるという紹介のされ方も見かけますが、正確には節税ではありません。
むしろもともと支払わなければならない税金の額より2,000円多く税金を支払うことになります。
と思うのはちょっと待ってください。
2,000円多く税金を支払う代わりに返礼品が受け取れるというのがミソです。
つまり「2,000円<返礼品」となればお得ということであり、基本的に2,000円を下回ることはないので超お得制度ということになります!
返礼品の金額は寄付金の30%未満と定められているため、1万円寄付した場合には最大3,000円相当の返礼品が受け取れるわけです。
と思うかもしれませんが、寄付できる金額にはもちろん上限があります。
この上限はあなたの収入等によって決まってくるので詳しくはふるさとチョイスのサイトでシミュレーションしてみてください。
収入が多いほど上限額も高くなります。
つまり高収入の人ほどふるさと納税はお得な制度ということになります。
これに関してはあなたの好きな自治体、好きな返礼品を選べばOKです!
少し贅沢をして普段は買わないシャインマスカットなんかを選んでもいいですね。
ただしよりお得にふるさと納税を活用するのであれば、普段買うものを選ぶのがおすすめです。
例えば、お米や洗剤、ティッシュ、トイレットペーパーといったものを選べばかなりの節約に繋がりますよね!
より詳しくふるさと納税制度について勉強したい方はこちら
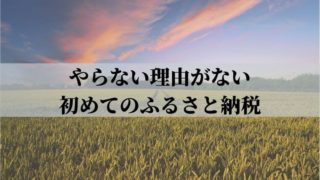
Step2おさらい
- お金を守るために制度を理解し、行動しよう
- なんとなく銀行にお金を預けているだけでお金が減っていく
- ポイントを活用しないともったいない
- 不幸が起こるのを期待するような保険の入り方はダメ
- もし保険が必要だったときには生命保険料控除が受けられる
- ふるさと納税は税金を2,000円多く支払う代わりに返礼品がもらえる
Step2~お金の守り方~は以上で終了です。
Step1は知識を蓄えることやお金の考え方を変えることが目的でした。
Step2では実際に理解した上で行動に移し、実際にお金を守ることが目的となっています。
なるほどなと思った項目だけでも構いませんので、実際に行動するとお金が守れることを実感してみてください。
ほんの少しの知識やコツだけで手元に残るお金は確実に増えていきます。
Step2~お金の守り方~をクリアした方は
Step3~お金の増やし方~でお会いしましょう!
当ブログはブログ村のランキングに参加しています。
「役に立った!」と思った方は以下のリンクをクリックしていただけますと
私が大喜びします!笑