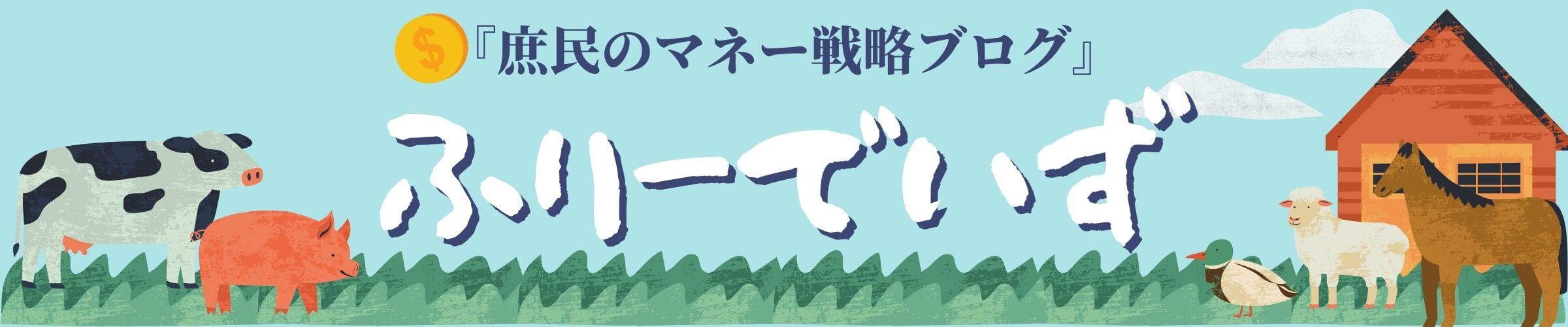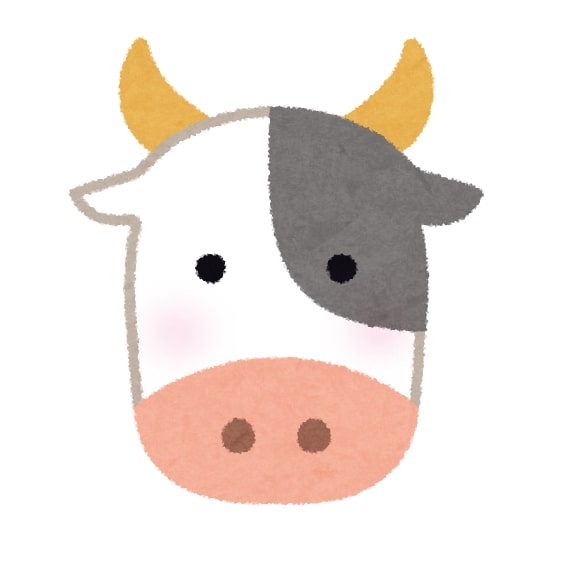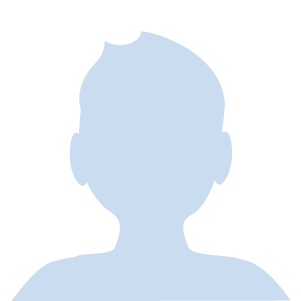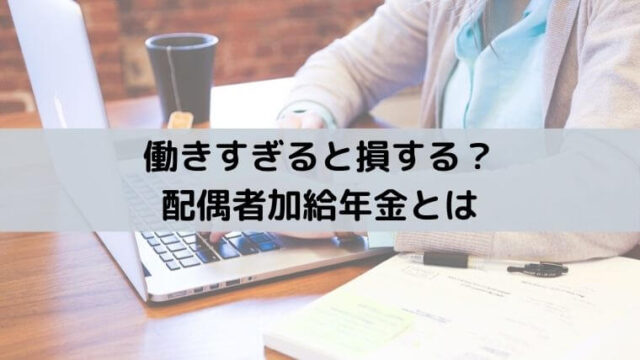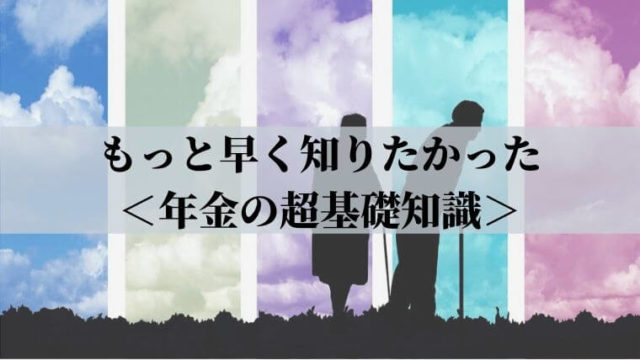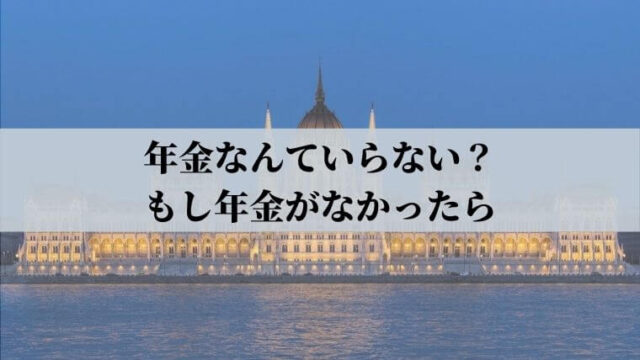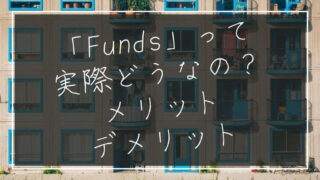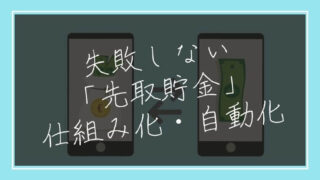この記事を読むとわかること
- そもそも年金とは何か
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金
- 支払う保険料の金額と受け取れる年金額の関係
- 年金は払い損かどうか
- 将来の年金額のシミュレーション方法
そもそも年金とは?
日本国内に住む20歳から60歳までの人は国民年金への加入が義務となっています。
加入するかしないか選べるものではありません。
また、社会保険に加入している会社で働く人は20歳未満から70歳までは厚生年金の加入が義務となっています。
厚生年金に加入し、保険料を支払っている人は国民年金の保険料も支払っている扱いとなります。

老齢年金とは?
年金は「もしもの時に収入がなくなってしまうのを防ぐこと」を目的とした保険であり、
(1)年を取って働けなくなった時
(2)障害を負って働けなくなった時
(3)一家の大黒柱が亡くなった時
に年金を受け取ることができる仕組みとなっています。
もちろん保険なのでちゃんと保険料を支払っていないと受け取ることができません。

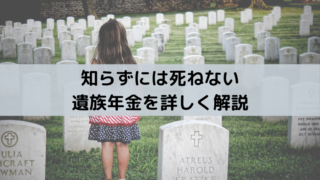
この記事で取り上げるのは
(1)年を取って働けなくなった時に受け取れる年金。その名も老齢年金です。
一般的には
国民年金に加入していた人が受け取れる年金は老齢基礎年金と呼び
厚生年金に加入していた人が受け取れる年金は老齢厚生年金と呼びます。
国民年金の保険料と老齢基礎年金の関係
国民年金の保険料は月額16,410円です。(令和元年度)
ではあくまでこの金額のまま、これを20歳から60歳まで支払った場合総額はいくらになるのか計算しますと
16,410円×480月=7,876,800円
なんと7,876,800円にもなります。
これは支払い続けることに疑問を持ってしまうのも納得の金額です。
払い損になることがわかっていれば絶対払いたくないですもんね。
では皆さんが一番気になる受け取れる金額はいくらかと言いますと
年額780,100円です。(令和元年度)
では何年受け取れば元が取れるのか計算してみましょう。
7,876,800円÷780,100円≒10年
約10年受け取れば元が取れるという計算です。年金は通常65歳から受け取れるため75歳まで生きればだいたい元が取れる計算です。
思っていたより悪くないのではないでしょうか。
厚生年金の保険料と老齢厚生年金の関係
では続いては厚生年金の保険料と老齢厚生年金の関係を見ていきましょう。
厚生年金の保険料は月給によって決まるため、モデルとなる人を想定し計算していきます。
今回は22歳から60歳まで(456月)平均月給30万円で働いた人をモデルとします。
・平均月給30万円
・厚生年金のみ加入
この場合厚生年金の保険料は30万円×18.3%=月額54,900円となります。ただし、厚生年金加入者はこの半額を会社側が負担してくれるため実際にモデルAが支払う保険料は月額27,450円となります。
つまり総支払保険料は
27,450円×456月=12,517,200円
なんと1000万円越えです。。。
では受け取れる年金額はいくらなのか!
老齢厚生年金の受け取れる額は以下の式で計算します。(ざっくり)
平均月給×(5.481/1000)×加入月数=老齢厚生年金の年額
つまり今回の例では
30万円×(5.481/1000)×456月≒年額749,800円
あれ?少なすぎない?と思った方は鋭いです。
これで元を取ろうと思うと17年弱かかりますので82歳くらいまで生きる必要があります。
いくら平均寿命が延びてるとはいえ、これはなかなか厳しい戦いになりそうですよね。
ただ、皆さん安心してください。
厚生年金加入者は国民年金にも加入していた扱いとなります。そのため支払う保険料総額は12,517,200円で変わらないにも関わらず、老齢基礎年金も受け取ることができます。
老齢基礎年金は以下の式で計算します。
780,100円×(加入月数/480月)=老齢基礎年金の年額
つまり
780,100円×(456月/480月)=年額741,095円
よって老齢厚生年金の年額749,800円と老齢基礎年金の年額741,095円を合計し
おおよそ年額1,490,000円受け取ることができます。
さてこれだとどれくらいで元が取れるでしょうか。
12,517,200円÷1,490,000円≒8.4
つまり8年と5か月ほどで元が取れる計算となります。74歳くらいでもう元は取れているわけです。
こちらも皆さんが思っているほど悪くないことがわかっていただけたのではないでしょうか。
まとめ
「もらえる年金額が少ないから保険料は払わない方がいい。」
「払い損になるから払いたくない。」
こんな意見をよく見かけますがこれは本当なのか疑問に思い検証してみましたが、思っていたより年金は悪いものではなさそうです。
ただし今後保険料が上がることや、もらえる年金額が減ることも考えられますし、賃金上昇率や物価上昇率、さらには平均寿命や少子化の影響等も考えるとこのような計算通りにいかないのはまず間違いありません。つまり必ず得とは言い切れません。
しかしそれでも障害を負った際や、亡くなった際の保険として年金が受け取れることや、ここには書けませんでしたが配偶者として第3号被保険者の方の年金額や加給年金といったものを考えると必ず損になるとも言い切れません。
要は誰にも将来のことはわからないのです。
それならば年金はどうせ義務なのでちゃんと保険料を納め、うまく活用する方法を考えていくことが大事なのではないでしょうか。
そして自身の年金の記録に関心を持ち、定期的にご自身の受け取れる年金額を確認しましょう。ちなみにねんきんネットを利用すれば将来受け取る年金の見込み額をシミュレーションできますので是非お試しください。