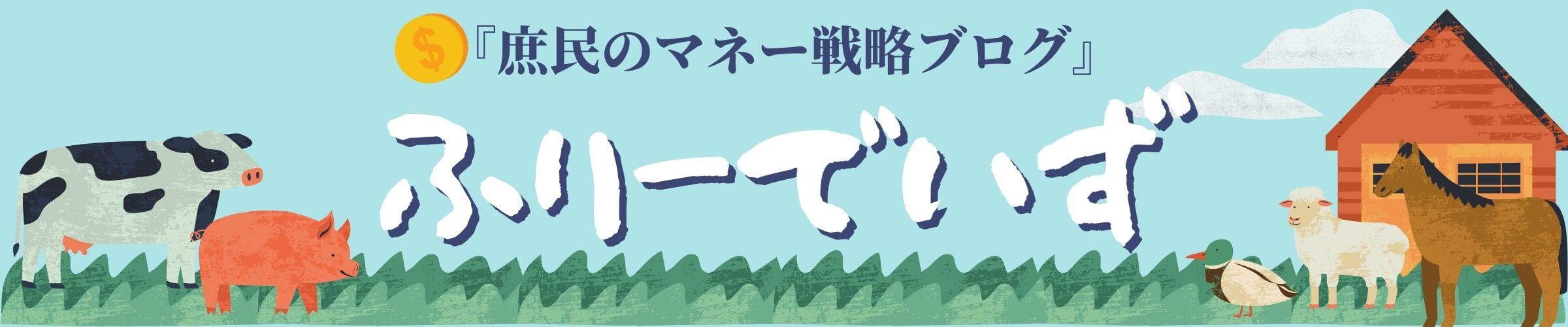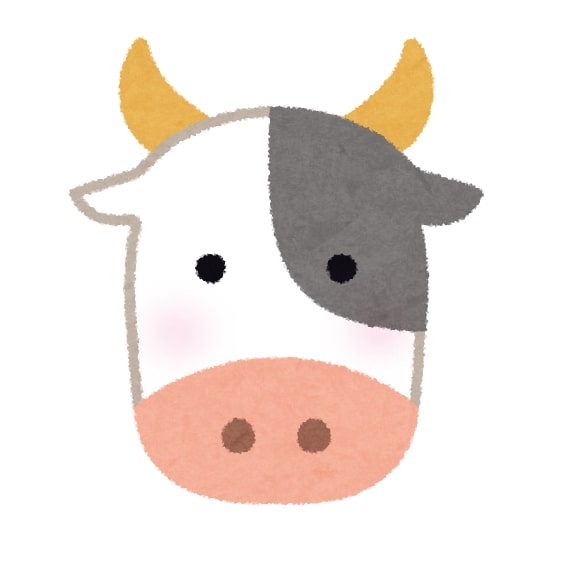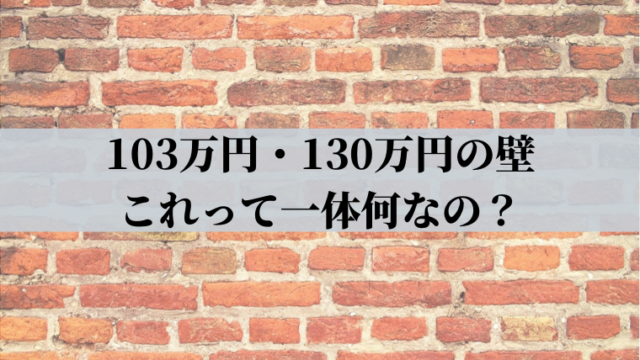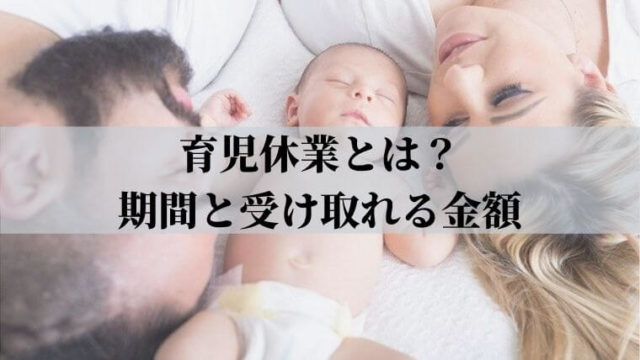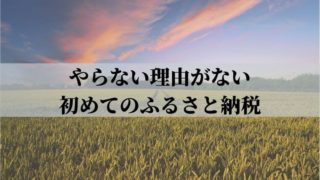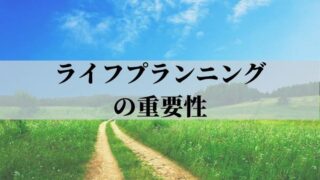生命保険に入っていると実は節税できるって知ってましたか?
よくわからないまま年末が近づくと会社に保険の書類を提出している方も多いかもしれませんね。
そして節税に繋がる保険は生命保険だけではありません!
- 生命保険料控除について知らなかった方
- 知ってはいるけど控除の考え方や計算方法がよくわからない方
はちゃんと理解しておきましょう!
- 生命保険料控除がなぜ節税になるのか
- 節税になる保険の種類
- 生命保険料控除の上限額
- 生命保険料控除の計算方法
※平成23年12月31日以前に契約した保険(旧契約)と平成24年1月1日以後に契約した保険(新契約)で扱いや計算方法が異なります。
この記事では難しい話は抜きでざっくり理解していただきたいので、新契約における生命保険料控除について紹介させていただきます。
生命保険に入っていると節税になる理由
生命保険に入っているとなぜ節税になるのかを理解するために、まずは税金の計算方法をおさらいしましょう!
税金の計算方法

税金というのはざっくり説明すると、全収入から所得控除分を引いて残った金額(課税所得)に税率をかけて計算されます。
(所得税も住民税も考え方は同じです。)
つまり
税金=(全収入ー所得控除額)×税率
となります。
例)収入が300万円・所得控除が100万円・税率が5%の人の場合
税金=(300万円ー100万円)×5%=10万円
となります。
所得控除の額が大きくなればなるほど税金も安くなるわけですね。
生命保険料控除で節税になる
生命保険に入っていると当たり前ですが保険料を払うことになりますよね。
この支払った保険料の一部は生命保険料控除という扱いになります。
もうお分かりですね?
生命保険料控除は所得控除の一種なので、課税所得を抑える効果があり、税金を安くすることができます。
つまり節税になるわけですね!
節税になる保険の種類と条件
生命保険料控除という名称ではありますが、控除の対象になるのは実は生命保険だけではありません。
以下の3種類の保険が対象となっています。
- 生命保険
- 介護医療保険
- 個人年金保険
①生命保険
- 生存または死亡に起因して一定額の保険金が支払われるもの。
- 保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするもの。
保険と聞いて一番にイメージするのはこの「生命保険」ではないでしょうか。
ざっくり説明すると、亡くなった時に保険金が出るタイプの保険のことですね。
変な保険の入り方さえしなければもちろん生命保険料控除の対象となります。
※保険期間が5年未満のものは対象となりません。
②介護医療保険
- 疾病または身体の障害等により保険金が支払われるもの。
- 医療費支払事由により保険金等が支払われるもの。
- 保険金等の受取人の全てをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするもの。
これもよくある保険ですね。
病気や事故で病院にかかった場合などに保険金が受け取れるタイプの保険のことです。
実はこれも「生命保険料控除」の対象となります!
※保険期間が5年未満のものは対象となりません。
③個人年金保険
- 年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをするもの、またはその配偶者となっている契約であること。
- 保険料等は、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
- 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として年金の支払いを開始する10年以上の定期または終身の年金であること。
「個人年金保険」はまだあまり知られていないかもしれませんね。
要は将来の年金の上乗せ分を自分で用意するタイプの保険のことです。
実はこれも「生命保険料控除」の対象となります!
条件が少し複雑に感じるかもしれませんが、長期にわたって保険料を積み立て、長期で年金を受け取る設定になっていれば問題ありません。
生命保険料控除の上限額
繰り返しになりますが、生命保険料控除は所得控除になります。
じゃあ、多ければ多いほど節税になるし最高じゃん!と思うかもしれませんが、もちろん上限額が決まっています。
所得税と住民税で上限が異なるので注意が必要です。
所得税編

生命保険・介護医療保険・個人年金保険、それぞれの控除上限額は最高4万円。
つまり合計12万円が「生命保険料控除の上限額」となっています。
住民税編

生命保険・介護医療保険・個人年金保険、それぞれの控除上限額は最高2.8万円。
しかし合計では7万円が「生命保険料控除の上限額」となっています。
生命保険料控除の計算方法
保険料の支払った金額の全額がそのまま控除の金額になるわけではありません!
所得税編
| 年間の支払い保険料 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
| 20,000円~40,000円 | 支払い保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円~80,000円 | 支払い保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
例)1年間で生命保険料を30,000円、個人年金保険を100,000円支払った場合の控除額は
生命保険分=30,000円×1/2+10,000円=25,000円
個人年金保険分=40,000円
つまり、合計控除額=25,000円+40,000円=65,000円
という計算になります。
住民税編
| 年間の支払い保険料 | 控除額 |
| 12,000円以下 | 支払い保険料の全額 |
| 12,000円~32,000円 | 支払い保険料×1/2+6,000円 |
| 32,000円~56,000円 | 支払い保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律28,000円 |
例)1年間で生命保険料を30,000円、介護医療保険を100,000円支払った場合の控除額は
生命保険分=30,000円×1/2+6,000円=21,000円
介護医療保険分=28,000円
つまり、合計控除額=21,000円+28,000円=49,000円
という計算になります。
(※合計が7万円を超えていた場合は7万円となる。)
無理やりでも生命保険に入るべき?
と思った方もいるかもしれません。
しかし生命保険料控除はあくまでおまけだと考えましょう。
保険料の金額を考える上で参考にする分には問題ありませんが、生命保険料控除のために無駄な保険に入っていては本末転倒です。
中には「生命保険料控除」が使えることを強調してくる保険会社の方もいますのでこの記事に書いてある最低限の知識くらいは持っておきましょうね。
まとめ
- 生命保険に入っていると節税になる
- 税金は収入から所得控除を引いた残りに税率をかけて計算する
- 生命保険料控除は所得控除の一種
- 生命保険料控除には3種類ある(生命保険・介護医療保険・個人年金保険)
- 生命保険料控除には上限がある
- 所得税と住民税で上限と計算が異なるので注意
いかがでしたか?
保険に入っていたとしてもここまで理解して入っている方ほとんどいないはずです。
節税のためと要らない保険に入っていては意味がありませんが、生命保険料控除をきちんと理解した上で改めて保険について考えてみてはいかがでしょうか。