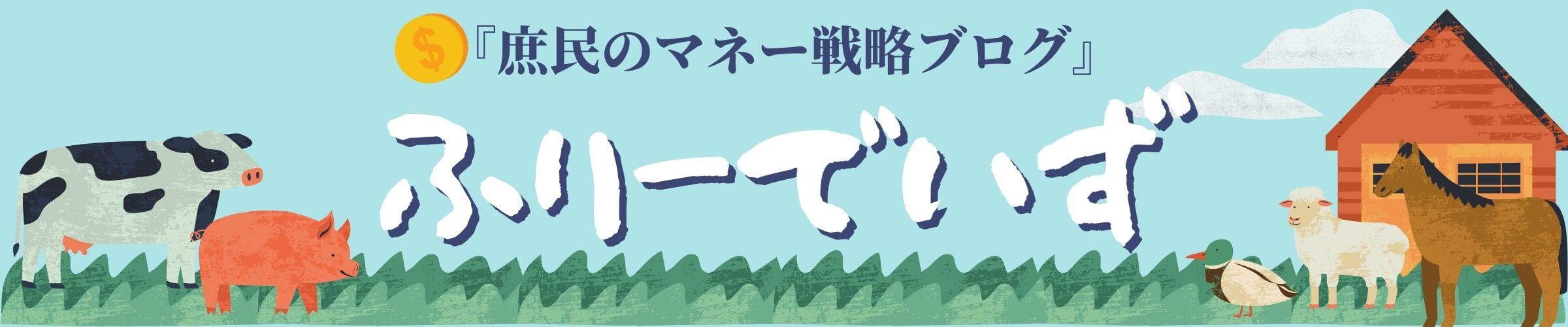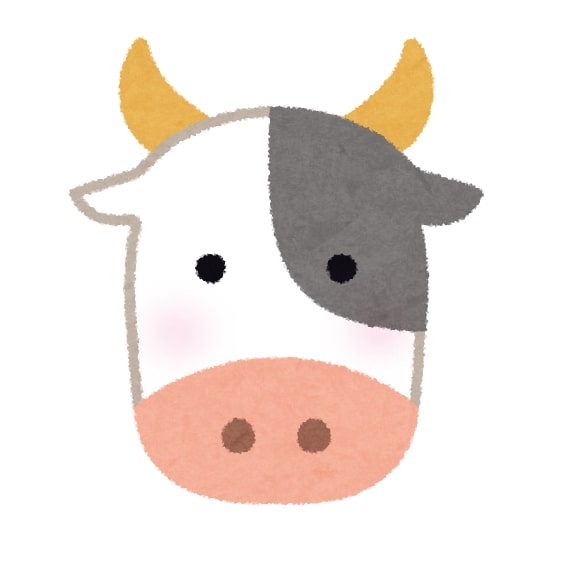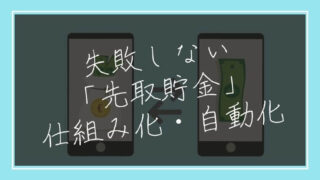この記事はこんな方におすすめ
- HSPの特徴を知りたい
- HSPと自己肯定感の関係が知りたい
- HSPが自己肯定感を上げる方法が知りたい
HSPの特徴

HSPは生まれつき周囲の人より繊細な感覚を持っている人のことを表す概念であり、病気ではありません。
五感がするどいため周囲からの情報を受け取り続け、考えすぎてしまうことで疲れやすいという特徴があり、一人の時間を大切にする傾向があります。
HSP以外の方にはよくわからない感覚かもしれませんが、耳栓をしていてもずっと音が聞こえてくるような感覚だと考えていただけると少しイメージしやすいかもしれません。自分の力でどうこうできるものではないのです。
HSPの概念はまだあまり浸透しておらず、内気、シャイ、人見知りと言われていたタイプがHSPに該当する可能性が高いです。
HSPについての詳しい説明はこちらにまとめています。
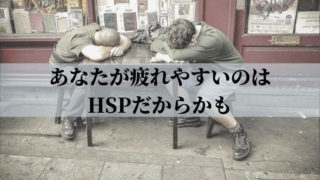
自己肯定感とは?

自己肯定感が低い人が多いなんて話がよく出てくるようになりましたが、実際に自己肯定感とは何を表しているのでしょうか?
自己肯定感とは自己価値に関する感覚であり、自分が自分についてどう考え、どう感じているかによって決まる感覚です。
そのままの自分を認め受け入れ、自分を尊重し、自己価値を感じて自らの全存在を肯定する「自己肯定感」の感覚は、何ができるか、何を持っているか、人と比べて優れているかどうかで自分を評価するのではなく、そのままの自分を認める感覚であり、「自分は大切な存在だ」「自分はかけがえのない存在」だと思える心の状態が土台となります。
引用元:一般社団法人日本セルフエスティーム普及協会(https://www.self-esteem.or.jp/selfesteem/)
ここに書かれているように自己肯定感とは自分で自分のことを価値がある、そのままでいいと認める感覚のことをいいます。
人がどう思うかであったり、人と比べてどうかということは一切関係ありません。
そして自己肯定感の高い、低いはその人の優劣を決めるものでは全くありませんが、自己肯定感の高低が人生に与える影響は大きいです。
一般的には自己肯定感が高い方が、自分に自信があり、やる気もあるため積極的に行動し、能力を発揮することができます。一方自己肯定感が低いと自分に自信がなく、消極的になり、能力を発揮することができません。
自分自身の評価だけでこのような差がつくのであれば誰もが自己肯定感を高めようと考えるでしょうし、実際にそのような自己啓発本なども発売されています。
私も様々な本やネットで自己肯定感を高める方法を探しました。
しかしいくら解決策を提示されたとしても自分では十分に自己肯定感を高めようとしてきた結果が今の自己肯定感の低さであり、改善につながる気がしませんでした。
実際にそのような本で救われている人もいる中で「なぜ私は自己肯定感を上げることができないのだろう」「私がおかしいのだろうか」と正直悩みました。
そんな時にHSPという概念に出会い、実はHSPと自己肯定感には関係があることを知り、気持ちが少し軽くなりました。
もし同じように自己肯定感が低くて悩んでいる方がいれば参考になるかもしれません。
HSPと自己肯定感の関係

HSPと自己肯定感って関係あるの?と思われる方も多いのではないでしょうか。
私自身もこの2つが関係しているとは全く思っていなかったので、たまたまHSPの本を読んでいたら自己肯定感の話が出てきてびっくりしたことを覚えています。
そもそも自己肯定感はどのように決まってくるのかを考えてみますと、赤ちゃんの頃から自己肯定感が低いという人はいません。成長する過程で育った環境や人生経験によって自己肯定感が形作られていきます。
一般的には親や周りの人から無視されたり、非難されたり、怒られたりすると自己肯定感は低下していきます。逆に褒められたり、自身の成功体験を通して自己肯定感が高められていきます。
ただしHSPの場合は少し異なってきます。
怒られたりすることにより自己肯定感が下がることは同じですが、基本的に怒られることを避けるために相手が何を求めているかを考えたり、察知して行動するようになります。
つまり自分が何をしたいのかよりも相手に合わせることを優先した行動を取り続けることになるわけです。

そして気が付けば自分自身に高い基準を定めてしまっている状態になります。
この状態の危険なところは「自分自身に価値がある」のではなく、「自分の行動に価値がある」と思い込んでしまっている点です。
相手はその高い基準を設けている自分のことが好きなのであってその基準をクリアできなければ「嫌われるんじゃないか」「友達が離れていってしまうんじゃないか」と考えてしまうということです。

自己肯定感が低いからこそ優秀であり続けるしかないわけです。
しかし高い基準をクリアし続けるのはそう簡単ではなく、クリアできなければそれによりまた自己肯定感が低下するという悪循環に陥ります。
これではHSPが疲れやすいのも納得ですね。
- 自分の意志と関係なく相手が求める行動を選んでしまう
- 自分自身ではなく行動に価値があると思い込む
- 高い基準を設定してしまう
- 自己肯定感が低下の悪循環に陥る
HSPが自己肯定感を上げる方法

当たり前ですが自己肯定感を上げるには、HSPの自己肯定感がなぜ低いのかを理解した上でそれとは逆の行動をとることが重要になってきます。
ここでは2つの対策を挙げてみましょう。
- 自分の意思に従ってみる
- 基準を下げてみる
①自分の意志に従ってみる
HSPにはやりたいことが分からない人も多いです。
というのも相手が何を求めているのか、どうすれば期待にこたえられるかばかり考えて自身の行動を決めてしまうからです。
始めはやりたいことがあったかもしれませんが、自分でも気づかないうちにやりたいことが分からなくなっていきます。
これでは自分の人生ではなく他人の人生を生きているような状態ですね。
ここで注意したいのはあくまでもやりたいことがないわけではなくわからなくなっているという点です。
HSPは常に考えており、その中にはやりたいこともあるはずなんですが、いろいろと理由をつけて頭の中に閉じ込めてしまっている状態なのです。

そこで自分の意思に従うことが重要になってきます。
ただしいきなり全部の行動を変えることは不可能でしょうから、10回に1回だとか自分のできる頻度で構いません。
最初は○○に行くだとか、○○を食べるといった些細なことからで構いません。自分の内側の声にほんの少し従うことから始めてみましょう。
自分で決めたことをやり遂げ、成功経験をつくることが自己肯定感を高める近道となります。
②基準を下げてみる
そしてもう一つの方法としては基準を下げてみることです。
私たちは意図的にというよりはほとんど勝手に相手が何を考えているか、何を求めているかを考えてしまいます。
そして相手が求める行動を取ろうとしてしまいます。
これは相手を怒らせないため、好かれるために行っていると考えられます。
しかしこれは自分のためになっているのでしょうか?

怒られないように、好かれるために相手のニーズを満たし続け、私たちHSPは神経をすり減らし続けなければいけないわけです。
いわば自分を偽り続けなければならないということです。
その偽りの自分を好きになってくれた人はあなたにとって本当に大事な人でしょうか。

本来の自分をさらけ出してもそばにいてくれる人こそがあなたにとって大切な人ではないでしょうか。
そしてそういう人づきあいこそがあなたの自己肯定感を高めることに繋がります。
まとめ
- HSPは生まれつき周囲の人より繊細な感覚を持っている人
- 自己肯定感とはありのままの自分を認める感覚
- HSPは自己肯定感が低い傾向にある
- 相手の求める行動を取り、やりたいことが分からなくなる
- 自己肯定感を上げるためには自分の意思に従い、基準を下げてみることが重要
自己肯定感を上げたい!と思っても今までのHSPとしての習慣をそう簡単に変えることはできませんので、できなくても全く焦る必要はありません。
実際私自身もまだまだ改善できていません。笑
しかし現状を把握しておくことはとても重要です。
まずは自分がHSPなのか。
そしてHSPは自己肯定感が低い傾向にあること。
なぜ自己肯定感が低くなるのか。
これを理解しておけばHSPのこういう特徴のせいで自己肯定感が下がっているんだなということが自分でもわかるようになります。
わかっていながら変えられないというもどかしさもあるとは思いますが何も知らなかった頃よりは着実に前進しています。安心してください。
HSP向けというわけではありませんが実は「嫌われる勇気」にもHSPの自己肯定感改善のヒントが多く書かれていますので気になる方は是非読んでみてください。